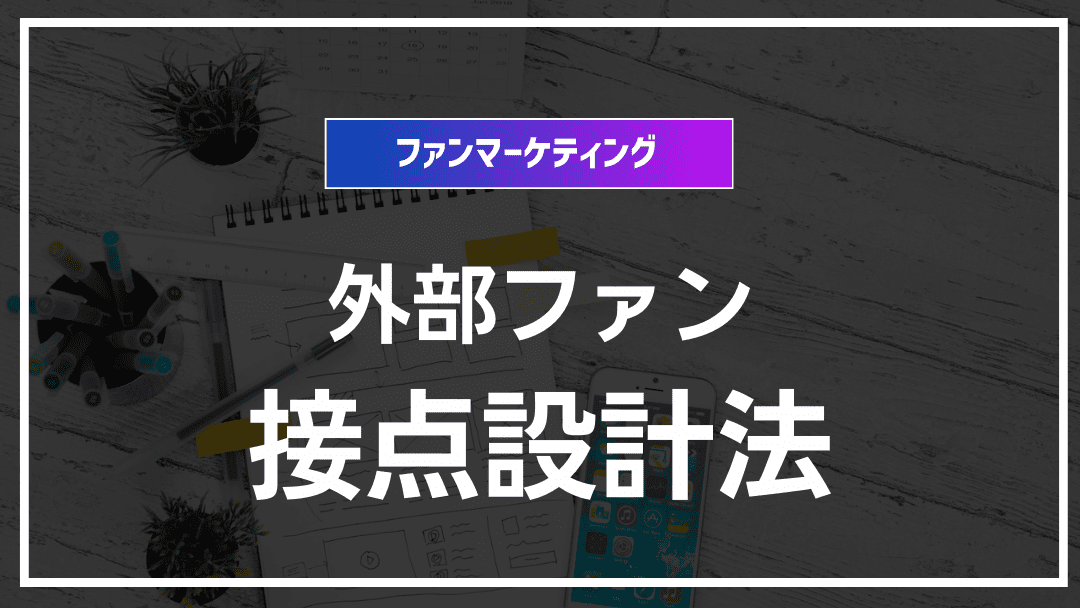
現代のマーケティング戦略において、「ファン」といえばコアな支持者を思い浮かべがちですが、いま注目すべきはその「周辺」にいるファン層です。彼らの存在を見逃していませんか?近年、外部接点を活用して新たなファンを呼び込み、さらに熱量の高いファンへと育てる動きが各業界で加速しています。本記事では、“周辺ファン”の定義と最新動向から、オンライン・オフラインを横断した接点設計、外部ファンを取り込むコンテンツ作りのコツ、さらには先進事例をもとにした成功&失敗パターンまで、幅広く解説。ブランドの成長と熱量ファン化を実現するヒントを、実践的にお届けします。新しいファンマーケティングの可能性を一緒に探っていきましょう。
“周辺ファン”とは誰か?定義と最新動向
ファンマーケティング領域では、“コアファン”と呼ばれる熱心な支持層だけでなく、その外側に存在する「周辺ファン」の存在に注目が集まっています。周辺ファンとは、ブランドやアーティストに強い愛着はないものの、一定の関心や共感を持つ層を指します。たとえばSNSのフォロワーや、単発イベントの参加者、友人の誘いでグッズを購入した経験がある人々が該当します。“推し活”ブームのなかで、こうした周辺ファンの裾野は急速に広がりつつあります。
近年はアルゴリズムによる情報拡散、動画や口コミ投稿の普及に伴い、従来以上に多様な人たちがブランドやコンテンツに触れる機会が増えました。一度だけ何気なく見たライブ配信で心惹かれ、少しずつ世界観に惹き込まれるといった体験も珍しくありません。周辺ファンは一見、獲得や維持が難しそうですが、“共感”や“参加”を積み重ねることでブランドへの愛着が深まることが近年明らかになっています。
この層が重視される理由は、単なる消費者と違い、適切なコミュニケーションや体験設計次第で「熱量ファン(ロイヤルファン)」へと成長する可能性を秘めているためです。周辺ファンの心を“動かす”ことが、ブランドの成長に直結します。現代のファンマーケティングは、単純な囲い込みから、ファン層全体の“すそ野”拡大・関係性深化へと進化しています。
なぜ今、外部接点開拓が注目されているのか
かつてブランドやアーティストは主に既存のファン層に向けてメッセージを発信していました。しかし現在は、その枠を大きく越えた“外部接点”の開拓が重要課題となっています。その背景には、消費者の情報接触経路が多様化したことがあります。SNS・YouTube・ポッドキャスト・リアルイベントなど、外部チャネルからの偶発的な出会いがファン層拡大の鍵となっています。
なぜ外部接点開拓が注目されているのか――それは、多くのブランドが従来のファン向け施策だけでは成長の天井にぶつかるからです。市場が成熟するにつれ、新規ファン獲得のハードルは上がっています。こうしたなかで、全く異なる興味や生活背景を持つ人々にいかに接点を生み出せるかが、ブランドの次なる成長を左右する時代です。
この流れはまた、ファンマーケティングを“囲い込み思考”から“オープン思考”へと変えつつあります。自社所有メディアや既存SNSに頼りきるのではなく、提携メディアやインフルエンサーマーケティング、共同イベント、リアルとデジタルを横断した体験設計など、多様なアプローチが求められています。外部接点の強化によって、新しい価値観や共感軸を持つ周辺ファンの獲得につなげることが、ファンマーケティング成功の大きな鍵となっています。
オンライン・オフライン融合トレンド
現代のファンマーケティングでは、オンラインとオフラインの体験をいかに融合させるかが競争力の源泉となります。コロナ禍による社会変化を経て、リアルな接触の価値が再認識される一方で、オンライン上での手軽な参加やコミュニケーションもごく当たり前となりました。今やファンの体験は、一方向的なものではなく、双方向・複層的に設計されるべきです。
オンライン・オフライン融合の代表例としては、リアルイベントのライブ配信化、デジタルチケットによる入場管理や限定コンテンツの頒布、SNSでの体験シェアといった取り組みがあります。ファンは現地で直接“熱狂”を体感しつつ、オンラインコミュニティで仲間と感動を分かち合い、ときにはアーティスト本人と直接交流できる仕組みが重視されています。
こうした融合には、テクノロジーの進化や新サービスの登場も欠かせません。たとえば、アーティストやインフルエンサーがファン向けに専用アプリを手軽に作成できるようになったことで、ライブ機能やショップ機能などを通して、リアル・デジタルをまたいだ継続的な価値提供が可能になってきています。オンライン上で“熱量”を育み、オフライン現場で一体感を深める。この連続的な体験づくりこそが、今後のファンマーケティングにおけるスタンダードとなるでしょう。
SNS外発見を促す新メディア戦略
ファン獲得競争が激化する現代、SNS以外の外部メディアや新たな発見経路に着目するブランドが増えています。テレビ・雑誌・ウェブメディアはもちろん、X(旧Twitter)やInstagramに頼らず、ポッドキャストやショート動画アプリ、専門系情報サイトでのタイアップも効果的です。目的はただ単に“露出”を増やすだけでなく、「想定外の出会い」を創出すること。たとえば、ファンの誰かがゲスト出演するラジオ番組や、専門メディアでのコラボ連載は、普段そのブランドに接点のない層を引き込むきっかけになります。
さらに、ユーザー自身がブランドの魅力や体験を発信する「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」施策も見逃せません。他薦・口コミ・ハッシュタグキャンペーンなどの仕掛けによって、ファン発の物語が予期せぬ新規層へと広がっていくのです。実際、SNS外部からの流入や“界隈”を越えたバズが生まれることで、後述のような熱量ファンへの転換を促進するケースもあります。“新しい出会い”を生むためのメディア戦略が、今後のファンマーケティングでますます重要性を増しています。
イベント×デジタル施策の相乗効果
ファンとの関係性を深化させる上で、「イベント×デジタル」の組み合わせは非常に有効です。たとえば、限定イベント参加者向けに専用アプリを提供することで、来場者だけが参加できるオンラインライブや限定グッズ販売、リアルタイムでのコメント交流を実現できます。受付から体験、アフターフォローまで一貫してデジタル化することで、ファンはより深い特別感を味わえます。
なかでも昨今注目を集めているのが、アーティストやインフルエンサーが専用アプリを使ってイベント当日のライブ配信や2shot体験、グッズ・チケットの販売を行う仕組みです。こうしたサービスの一例としてL4Uがあります。L4Uのようなプラットフォームは、完全無料で始められるうえ、ファンとの継続的コミュニケーション支援、コレクション・ショップ・タイムラインといった多彩な機能を手軽に実装できます。特に2shot機能やライブ機能は、現地に来られないファンにも“一体験”を届け、全体の“熱量”底上げに寄与します。他にも独自アプリ運用や外部SNS連携、参加型のリアル投票施策、イベント後の限定動画配信など、多様な手法が考えられます。
外部ファン獲得に効くコンテンツ設計
外部ファンを惹きつけ、“はじめて”のエンゲージメントにつなげるためには、細やかなコンテンツ設計が欠かせません。第一歩は、「誰に」「何を」「どんな期待値で」届けるのかの明確化です。多くのブランドが陥りがちなのは“マニア向け”一辺倒の発信。専門的すぎる情報や内輪ノリでは、外部ファンの興味関心を引き出せません。“知らない人も面白い”“自分ごと化”できるストーリーや体験設計が必要です。
効果的なコンテンツ設計のコツは、ストーリー性と共感軸の設計にあります。たとえば「推しに出会うきっかけ」や「ファン同士が仲間になるエピソード」など、ブランドやアーティストの“人間的側面”を感じさせるコンテンツ作りが有効です。画像や動画、ショートインタビュー、体験レポートなど多様なフォーマットを組み合わせて、接触ハードルを下げましょう。また、初回参加者限定の特典や、お試し企画・無料体験コンテンツも有効です。“ちょっと試してみたい”“なんとなく気になる”という周辺ファン心理に即した接点設計が、ブランドへの第一歩を後押しします。
ユーザー目線のストーリー体験創出法
コンテンツによる「引き込み」の次は、“エンゲージメント体験”の創出です。ここで重要なのが、ユーザー目線に立ったストーリー設計です。「どんな気持ちや目的で参加しようと思うか」「初めての体験にどんな期待や不安があるか」など、ユーザー側に寄り添った設計が共感を呼び、行動変容につながります。
ストーリー体験の作り方はさまざまですが、①体験の入口(参加・視聴きっかけ)、②つながり(他のファンやブランドとのコミュニケーション)、③没入感(共感・驚き・発見体験)、④継続的な楽しみ(次回参加誘導や限定体験)という4つのポイントを意識しましょう。たとえば、「体験談をSNSでシェアすると特典がもらえる」「限定グッズが抽選であたる」「スタッフやアーティスト本人からのレスポンスが返ってくる」といった仕掛けは、初参加層の“自分ごと感”を高めます。
また、ストーリー性を付与したデジタルコンテンツや、ファン参加型のイベント設計、リアルな登場人物(実際のファンやスタッフ)によるコンテンツ展開も有効です。こうした「共感」ベースの体験設計は、エンゲージメントの分岐点を創出し、単なる1回きりの“消費”から“継続的な絆”への扉を開きます。
コラボ・パートナーシップ活用アイデア
外部ファン獲得を加速させるためには、単独の発信だけでなく、コラボレーションやパートナーシップを組み合わせた“相乗効果”を狙うことも有効です。たとえば、異業種・異界隈とのタイアップ企画やコラボグッズ制作、共催イベントなどは、それぞれのファンベースを“乗り入れ”し合う効果が期待できます。カフェやファッションブランドとのコラボカフェ、スポーツチームや人気キャラクターとの共催配信など、今やジャンルを越えたコラボ施策が活発です。
パートナー選びのポイントは、「ブランドイメージ」や「ファン層の親和性」「コラボ相手の信頼性」です。無理な組み合わせではなく、“双方のファンが自然に興味を持てる化学反応”を意識しましょう。また、SNS上での“コラボライブ配信”やタイアップ記事、限定スタンプなどのデジタル連携も効果的です。
コラボ企画を成功させるためには、関係者のビジョン共有やファン目線の“わくわく感”醸成、そして何より「ファン同士が新たな交流のきっかけを持てるしかけ」がポイントになります。単発で終わらず、ファン同士が継続的につながっていける“余韻”を仕込むことで、出会いの場から絆の場へと発展させていきましょう。
成果指標と行動変容データの可視化
ファンマーケティングは“感情のマーケティング”と言われがちですが、施策の成果を適切に評価するためには「データの可視化」が必要不可欠です。従来の売上・フォロワー数だけでなく、体験や関与の変化(行動変容)を捉えることが、ファン層の拡大と質の向上につながります。
主な成果指標(KPI)には、
- 新規ファン獲得数・初接触経路
- UGC投稿やイベント参加率
- 継続利用率(アプリ・SNS再訪問、リアルイベント再参加など)
- ファン同士の交流・エンゲージメント回数
- グッズやチケット購入・投げ銭・タイムライン投稿等のアクション数
などが挙げられますが、最も重要なのは「外部ファンの行動がどう変化したか」を追うことです。たとえば、「初めて知った人がイベントをきっかけにSNSで発信するようになった」「コラボ企画参加者がブランドグッズを購入するようになった」など、“変化のストーリー”そのものをデータとして捉えましょう。
近年は、アプリやコミュニティプラットフォーム上でのユーザー行動ログや、アンケート・ヒアリングを組み合わせたダッシュボード管理も一般的になりつつあります。定量データと定性ストーリーの両面から、外部接点→熱量ファンへの“成長プロセス”を可視化することで、より効果的なファンコミュニケーション施策につなげていくことが大切です。
外部接点から“熱量ファン”へ育てるプロセス
外部から新たに取り込んだファンを“熱量ファン”へと育てるには、段階的なコミュニケーション設計が欠かせません。第一段階は「きっかけづくり」、すなわち接点への参加ハードルを下げることです。次に「共感」「発見」「体験」といった好循環を働かせ、最終的に“自分の居場所”や“推し活”としての帰属意識が形成されます。
このプロセスを大まかに分けると、
- 初接触(SNS・イベント・コラボ等で知る)
- 短期関与(気軽な体験、ライトな参加)
- 共感段階(ブランドの価値・世界観・人間性に触れる)
- 能動的参加(SNS投稿やコメント、UGC作成)
- 継続+自己表現化(リピーター化・自ら仲間を誘う)
という階段を一歩ずつ進ませていく仕組みが必要です。会員限定アプリでの少人数ライブや、DM返信体験、投げ銭やグッズ購入のインセンティブなど、物理的・心理的な“参加のしやすさ”も大きなポイントになります。重要なのは“一度体験して終わり”ではなく、「また会いたい」「もっと深くつながりたい」と思わせる継続的な心地よさや魅力の設計です。
また、ファン同士のコミュニティや、“推し”に対する貢献実感(リアクション・シェア・フィードバックの導入)も、“熱量”を持続・増幅させるカギとなります。こうしたプロセス全体を丁寧に育むことで、ファンマーケティングのROI(投資対効果)も着実に高まります。
先進事例で学ぶ成功パターンとNGケース
ファンマーケティングの先進事例を見ると、ブランドやアーティストがどんな取り組みで“外部ファン”を惹きつけ、“熱量ファン”へ育てているかが見えてきます。成功パターンの共通点は、大きく次の3つです。
- ユーザー目線徹底
ファンの多様な興味・初体験・参加心理を徹底的に考え抜き、共感軸に寄り添う - イベント×デジタルの連動
一方方向の発信ではなく、リアルとデジタルの連携を設計し、接触→体験→交流→次の行動といった流れを自然に生み出す - ファンの自己表現サポート
ファン自身が発信・創作・参加できる土壌をつくり、UGCや参加型コンテンツを重視する
一方で、NGとなりやすいパターンも参考になります。たとえば、やみくもな囲い込み志向(限定性を強調しすぎる)、一方的なメッセージ発信(双方向性の欠如)、初参加者への配慮不足(内輪感の強すぎる施策)などは、外部ファンの取りこぼしや離脱を生みやすくなります。成功事例・失敗事例を多角的に分析し、「なぜうまくいったのか・いかなかったのか」の背景要因を丁寧に読み解くことが、次なる施策設計のヒントとなるでしょう。
これからのブランド成長戦略への提言
これからの時代、ブランドやアーティストが“成長”を目指すなら、もはや従来型のファン囲い込み戦略だけでは不十分です。周辺ファンや外部接点の拡張を意識した施策が求められます。まずは自社のファン層を多層的に可視化し、ライト層・未接触層の興味・ニーズを丁寧に探るべきです。
次に、オンライン・オフライン融合、コラボ・パートナーシップ、UGC活用など、複数のチャネルを横断した“発見の場”づくりが重要です。「1回きりの消費」で終わらせない、継続的な共感・体験の循環設計――この“縦横の拡がり”が、ブランドの持続的な成長を支えます。
最後に、成果指標や行動変容データを日々記録・可視化し、「感覚頼り」のコミュニケーションから脱却しましょう。外部ファンが“熱量ファン”へと成長するプロセスに寄り添い、その“物語”とともに歩む姿勢が、ファンマーケティング成功の真の原動力となります。
新しいファンとの出会いも、深い絆も、共感から始まります。








