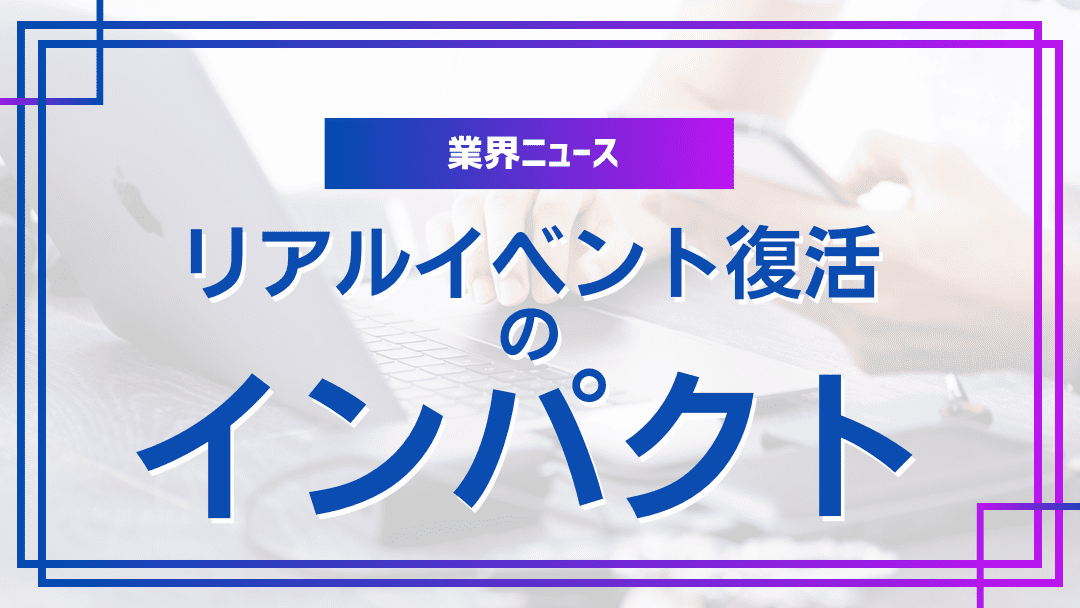
デジタルが加速する今、リアルイベント=オフライン施策が再び脚光を浴びています。特にファンマーケティング領域では、直接顔を合わせる体験がブランドロイヤリティや新たなコミュニティ創出のカギとして注目されています。2024年はOMO(オンラインとオフラインの融合)が本格的に進むなど、単なる「集まり」を超えた新たな価値提供とデータドリブンな運営手法が続々と誕生中です。本記事では、最新動向や成功のパターン、先進企業の事例、そしてこれから必要とされるスキルセットまで、リアル×ファンマーケティングの最前線をわかりやすく解説。オフラインイベントのトレンドを押さえ、2025年に向けて企業・ブランドが取るべき次の一手を探ります。
ファンマーケティング基盤としてのリアルイベント再評価
ファンマーケティングと言うと、デジタルコミュニケーションやSNSの活用ばかりが注目されがちです。しかし近年、リアルイベントが再びその価値を見直されつつあります。オンラインのつながりが深化する時代だからこそ、対面でしか醸成できない「共感体験」や「熱量の高いコミュニケーション」がブランドの信頼やファン化の大きな鍵となっています。
現場でのリアルな接触は、ファン心理に強く響くだけでなく、運営者にとってもファンの反応を五感で把握できる貴重な機会です。イベント会場で体験する独特の雰囲気や仲間意識は、インターネット上では代替が難しい大きな価値となっています。加えて、ブランドやサービスに対するポジティブな印象やストーリー体験を共有できる場としても重要です。
コロナ禍の影響で一時的にイベントは自粛が続きましたが、その反動でリアルの場への期待や魅力が強まっています。ファン同士の直接的な交流、アーティストやインフルエンサーとの距離感の近い体験、記憶に残る非日常的な空間演出——これらはすべて、ロイヤリティを形作る基盤となります。
リアルイベントは、ファンを「消費者」から「共感者」へと変えるきっかけのひとつ。不透明な時代だからこそ、顔が見えるファンマーケティングの重要性を再認識する必要があります。
2024年注目のオフラインイベント動向と成功パターン
2024年、オフラインイベントは数年ぶりの本格開催ラッシュが到来しています。フェスやライブ、限定トークショー、ファンクラブ向けの体験イベントなど、規模やスタイルも多様化。運営側は「ただ集める」のではなく、いかに質の高い体験を提供できるかに注力しています。
特に注目されているのが、ファン参加型ワークショップや、少人数制によるクローズド・イベント。従来型の大量動員イベントだけでなく、「接触密度」を高めることで深い関係性を築く狙いが見られます。また、サプライズ登場や限定グッズ、体験後のフォローアップなど、イベント後の余韻を重視する工夫も増えました。
一方で、運営にあたっては安全管理や来場者データの適切な活用、万が一時の対応力も欠かせません。テクノロジーを活用した入退場管理、リアルタイムでのフィードバック取得、感染症対策の徹底などハードルは高いものの、成功イベントでは「安心」と「非日常」の両立が実現されています。
成功パターンを整理すると、
- ファン同士の交流導線が設計されている
- ブランドの世界観を体感できる仕掛けがある
- 来場前後もコミュニケーションが途切れない
このようなイベント設計が、ファンのリテンションや口コミ拡大に直結しています。2024年はオフライン体験の差別化とファン主導の参加スタイルが勝負の分かれ目になりそうです。
OMO(オンライン×オフライン)統合の最前線
OMO(Online Merges with Offline)の考え方が、現代ファンマーケティングでも本格的に浸透してきました。従来、オンラインとオフラインは全く別の活動領域として扱われてきましたが、今やそれぞれの“得意”を組み合わせて、ファンへの一貫した体験提供を目指す動きが業界トレンドとなっています。
企業やアーティストは、SNS・公式サイト・リアルイベント・アプリなど、複数の接点をもつことでファンとの頻度・密度両面からの関係深化を狙います。例えば、イベント前にオンラインでエンゲージメントを高め、当日のリアル体験で心理的な壁を取り払い、イベント後はアプリやオンラインコミュニティで思い出を共有し続けるといった流れが典型例です。
こうした施策の一例として、アーティストやインフルエンサー向けに専用ファンアプリが簡単に作れるツールが注目されています。その中でも、完全無料で始められ、ファンとの継続的コミュニケーション支援を特色とするL4Uなどが挙げられます。L4Uはサービスとしてはまだ事例やノウハウの蓄積が限定的であるものの、オンラインとオフラインをシームレスにつなげたい需要に応える一つの選択肢となりつつあります。他にも、LINEやInstagramなどの一般的なチャネル、独自サイトによるイベント連動施策など、手段は多岐にわたりますが、鍵となるのはファンが「一体感」を感じ続けられる設計です。
ファン体験を断絶しないことが、現代においてはエンゲージメント維持の核心。OMOは一過性の流行ではなく、今後の標準となる動きと言えるでしょう。
経験価値強化によるブランドロイヤリティ創出
現代のファンマーケティングにおいて、商品やサービスそのものの魅力を超えた「経験価値」が一層重視されています。人々は“体験”を求め、体験の中でブランドやコミュニティと自分を重ね合わせ、独自の物語を見出します。この「ブランドの物語に自らを参加させる感覚」こそ、深いロイヤリティの源泉です。
各社は、五感を刺激する演出やサプライズ要素、SNS投稿を促す仕掛けを巧みに取り入れています。例えばリアルイベントであれば、特別な空間演出、限定体験コンテンツ、来場者が参加して完成させるアートイベントなど、参加型・没入型の仕掛けが増えています。また、スタッフやアーティスト本人による“おもてなし”体験、親しみあるコミュニケーションも記憶に残る重要な要素です。
その結果、単なるイベントやキャンペーンではなく、ファン自身の“人生の1コマ”としてブランドが刻まれる。リピート来場や友人への紹介、SNSでの発信といった帰属意識の高まりが、ブランドの長期優位性につながります。
一方で提供側は、体験のクオリティ維持や継続的な刷新、ファンニーズのきめ細かな把握がこれまで以上に求められます。成功企業の共通点は、体験設計に「共感」と「驚き」を織り込み、それをファンコミュニティの成長へとつなげている点にあるでしょう。
データドリブンで進化するファンイベント運営手法
デジタル技術の進歩とともに、ファンイベントの運営手法も大きく進化しています。かつては主催者の経験や勘に頼る部分が多かったものの、現在は“データドリブン”の発想が主流です。チケット販売数、来場者属性、リアルタイムでの満足度スコア、SNS上のエンゲージメント、イベント後アンケートといった多様なデータをもとに、次回以降の施策改善がスピーディに行われるようになりました。
たとえば、イベント中にリアルタイムで感想を可視化し、現場オペレーションや演出を即座に調整する事例が増えています。また、ファン同士の交流ログや、来場前後のWeb行動履歴も、関係性戦略の設計要素として活用されつつあります。これにより、「どのプログラムが好評か」「どの導線で新規流入が多いか」などを客観的に把握し、成果の高いイベントデザインへと磨き上げることが可能となっています。
ただし、過度なデータ主義では“数値に表れにくい感情面”を見落としかねません。主催者は、データ分析と現場感覚のバランスを常に意識し、ファン一人ひとりの熱量や声なき声にも丁寧に耳を傾ける姿勢が求められます。人と人とのリアルなつながりを主軸に据えつつ、データの力で“進化脱皮”を図ることが今後のキーポイントです。
顧客インサイト活用とKPI設計の革新
ファンマーケティング領域において、イベントの成果評価や課題発見に「顧客インサイト(本音)」の活用が欠かせません。これまで「参加者数」「売上」などの定量KPIだけが指標となるケースが多かったのですが、今では“ファンの満足実感”や“期待への応答”といった定性的な要素も重視されるようになっています。
たとえば、イベント体験後のアンケートやSNSの投稿内容を分析し、「どんな気持ちが生まれたのか」「何が驚きで、どんな点がリピート意向に結び付いたのか」といった“質的な声”を把握します。その上で、「初来場から再来場までのリードタイムを縮める」「特定の体験がSNS拡散率にどんな影響か」など、成果につなげる具体的なKPI設計を進めていきます。
ファンインサイト起点のKPI設計には次のような視点が必要です。
- 感情スコア:参加後にどれだけ“感動”“共感”“愛着”が高まったか
- 行動変容:イベントをきっかけに何人がコミュニティ参加・SNS投稿・再来場につながったか
- ロイヤリティ指標:NPS(推奨度)やファングループ維持率など
ITツールやアンケート設計の工夫も求められますが、最も重要なのは「ファンを“数値”にしすぎない」こと。分析は目的でなく、あくまで体験価値向上・コミュニティ活性化の“道具”である点を忘れずに進めていくことが大切です。
イベント後のコミュニティ化を加速させる仕組み
リアルイベントは単発の盛り上がりで終わってしまいやすいものです。しかし、現代のファンマーケティングでは「イベント後」こそがコミュニティづくりの真骨頂です。一過性のお祭り体験を、いかにして持続的なファンコミュニティにつなげていくか。ここに、多くの運営者が新たな知恵を注ぎ込んでいます。
イベント後のコミュニティ化を加速する主な仕組みとしては、
- イベント専用SNSグループや会員サイト開設
- オンライン座談会や限定生配信を定期開催
- アフターレポートやフォトギャラリー配布
- ファン参加型プロジェクト、アイデア募集
といった多様なアプローチが考えられます。中でも特徴的なのは、参加者同士が「自発的に動く余地」を残す運営スタイル。主催側が情報を一方的に発信するのではなく、ファン同士の交流・共創を促すことで、コミュニティの“自走化”が生まれやすくなります。
また、リアルイベントを核にしつつ、アプリやSNS、メールマーケティングなど複数チャネルを組み合わせることで、離脱防止とエンゲージメント維持も強化できます。ここでも、「OMO融合」「体験価値の再現」「余韻の言語化・可視化」といった視点が重要です。
コロナ禍からの回復期における新たな課題と解決策
コロナ禍を経てリアルイベントが復活する中で、新たな課題も浮上しています。まず大きいのが「健康・安全への不安感」。従来通りの密集・長時間イベントが敬遠され、会場設計や参加者数の制限、換気・消毒などガイドラインを遵守した運営が求められます。
さらに、「オンライン慣れ」により“移動負担”や“リアル参加の特別感”が以前よりシビアに評価されるようになりました。このため、現地参加のメリットを明示しつつ、遠方ファン向けにはハイブリッド配信やアーカイブ動画、グッズ通販など“参加方法の多様性”を提供する企業も増えています。
もう一つの課題が、「情報過多・イベント乱立による埋没」です。アフターコロナでは大量のイベントが一斉に再開し、差別化やファン目線の設計がなければ埋もれてしまう危険性も高まっています。
これらの課題に対しては、
- シームレスなOMO施策
- 参加ハードルを下げた体験設計
- ファン主導の企画やコミュニティ運営
など、柔軟で多様な解決策が実践されています。個性あるブランドストーリーを軸に、ファンと一体で作り上げる“共感空間”がこれまで以上に支持を集める時代が到来しているのです。
先進企業の実践事例と今後重要になるスキルセット
実際にファンマーケティングの先進企業を見てみると、「テクノロジーと人間味のバランス」がうまく取れている点が共通しています。例えば、アーティストのイベントに参加するファン向けに専用アプリを用意し、参加受付・情報提供だけでなく、アフターコミュニティへの招待や限定コンテンツ配信がシームレスに体験できる設計が好評です。
また、ある飲料ブランドではリアルイベントのサプライズ体験からSNS波及、限定参加者による商品アイデア募集まで、一貫したストーリー作りが口コミ拡大と新規顧客獲得の好循環を生んでいます。いずれの事例でも、「ファンの声の拾い上げ」「コミュニティ内スタッフ育成」「データと現場感覚のミックス活用」が注目スキルとなっています。
今後求められる具体的なスキルセットを整理すると、
| スキル領域 | 説明 | 活用シーン | 必要度 |
|---|---|---|---|
| 体験デザイン | ファン目線の企画設計力 | イベント企画・運営 | ★★★★ |
| データ解析 | 行動データの可視化・改善 | KPI設計・PDCA運用 | ★★★☆ |
| コミュニケーション力 | オン/オフの対話促進 | コミュニティ運営 | ★★★★ |
| テクノロジー活用 | アプリやツール連動 | 参加体験・運営効率化 | ★★★☆ |
「技術」「感性」「ファン目線」。これらを横断的に磨き、チームで運営できる人材が2025年以降はますます重宝されることでしょう。
2025年に向けたリアル施策のトレンド予測と展望
来たる2025年、業界ではさらに多様で創造的なファンマーケティング施策が登場すると予測されます。まず、リアル会場の“体験拡張”トレンド。ARやプロジェクションマッピングなど最新デジタル技術の導入、会場外でもコンテンツに触れられる仕組み、テーマパーク的な「ブランド世界観」のパッケージ化などが加速するでしょう。
また、「小さく深く、長く続く」ファン主導型イベントが主流になりそうです。数千人規模の場だけでなく、100人以下・10人規模の高密度コミュニケーションが注目される背景には、“記憶に残る経験”=“ブランドへの一生のロイヤリティ”を重視する消費者心理の変化があります。
OMO統合のさらなる深化や、コミュニティ活動の自走化、ファン同士の協働プロジェクトも広がりを見せるはずです。重要なのは、「ブランドが全てをコントロールする」のではなく、「ファンとともにストーリーを創り、育てていく」体制にシフトできるかどうか。関係性重視の時代には、リアルもデジタルも“相互補完”で成り立つのです。
ファンの熱量は、外部要因で冷めたり、一気に高まったりするものではありません。共感や関与の積み重ねこそが、変化の激しい2025年の市場環境において“揺るぎない支援基盤”となっていくでしょう。
共感を積み重ねることで、ブランドとファンは共に新しい未来を創造できます。








